
パリパリポリポリ、パリパリポリポリ・・・らっきょうって、美味しいですよね。
我が家では2015年から、らっきょうを漬け始めました。
らっきょうを漬けるきっかけになったのは、母に言われたこの言葉。
「らっきょうは体に良いから食べなさい」
言われるまま甘酢漬けと醤油漬けを作って食べてみたのですが・・・
実はどんな栄養や効能があるか、あまり気にしたことなかったのです^^;
そこで今回は、今まで気にせず食べてきた
・生らっきょうと甘酢漬けの栄養
・らっきょうの効能
この2点について、調べたことをご紹介します^^
生らっきょうと甘酢漬けの栄養価。甘酢漬けは栄養価が少ない
らっきょうは甘酢漬けにした場合、生らっきょうより栄養価は少なくなります。
生らっきょうを刻んで食べると、そのまま栄養を得られます。
栄養成分で注目されるのは、らっきょうの食物繊維含有量です。
なんと、可食部100g当たり21gもの食物繊維が含有されています。
では他の栄養は何があるのでしょうか?
生のらっきょうと甘酢漬けの栄養成分をわかりやすく表にしました。
※七訂日本食品標準成分表をもとにした可食部100g当たりの栄養素の量です。
※栄養の隣の()内は成人女性の1日の推奨量または目安量です。
| らっきょう(生) | 甘酢漬け | |
| エネルギー | 118kcal | 115kcal |
| カリウム(2000mg) | 230mg | 38mg |
| ビタミンE(6.5mg) | 0.8mg | 0.2mg |
| ビタミンC(100mg) | 23mg | 0 |
| ナイアシン(12mg) | 2.1mg | 0.2mg |
| 食物繊維(17g) | 21g | 3.1mg |
上記の成分以外にも微量ですが、ミネラルを含んでいます。
生らっきょうの食物繊維は『水溶性が18.6g、不溶性が2.4g』の割合です。
他の野菜と食物繊維の含有量を比較してみると・・・
ごぼうの4倍、キャベツの11倍もの食物繊維の差があるんです!!
らっきょうは野菜類のなかでも、トップクラスの食物繊維量なんですよ^^
 お通じが快適になるかも♪
お通じが快適になるかも♪
腸内環境が整い、便秘が改善するだけでも肌の調子は変わります。
![]() 甘酢漬けは栄養が減るけど汁ごと食べて!
甘酢漬けは栄養が減るけど汁ごと食べて!
らっきょうは甘酢漬けにすると栄養価は減少し、ナトリウムが860mgに増加します。
食物繊維の効果を期待するなら、甘酢漬けよりも生食がいいでしょう。
しかし、カレーなどの付け合わせで食べるらっきょうは、汁ごと食べることにより少ない栄養を効率的に摂取することができます。
甘酢漬けの場合も、汁ごと食べることをおすすめします。
では続けて、らっきょうの効能について詳しくご紹介しますね!
らっきょうのフルクタンと硫化アリルの効能がスゴイ!
らっきょうは食物繊維の『フルクタン』と『硫化アリル』の効能に注目です。
野菜からは摂取しにくい水溶性食物繊維です。
腸内の善玉菌のエサになりやすく、腸内環境を改善する効果が期待されます。
また、腸内環境を整えることで免疫力アップにもつながります。
フルクタンの効能
などがあります。
特に福井県産のらっきょうはフルクタンが90%と豊富に含まれています。
フルクタンの血糖値上昇抑制の研究結果PDFがあります↓
『食物摂取後の血糖値上昇に及ぼすラッキョウフルクタンの影響』
またコレステロールが高めの人にフルクタンを摂取させると、
血中コレステロール値が低下したという研究も確認されています。
含硫化合物のうちの1つでニンニクや玉ねぎなどにも含まれています。
硫化アリルの代表的な成分にアリインがあります。
アリインは体内に入ると、強力な殺菌作用があるアリシンに変化します。
硫化アリル(アリシン)の効能
![]() 強い香りが胃酸の分泌を促して消化を促進し、食欲を増進させる
強い香りが胃酸の分泌を促して消化を促進し、食欲を増進させる
![]() ビタミンB¹の働きを助け、血行を良くし疲労を回復する
ビタミンB¹の働きを助け、血行を良くし疲労を回復する
![]() 強い殺菌作用による口内炎の予防
強い殺菌作用による口内炎の予防
![]() 血液をサラサラにして血糖値を下げる
血液をサラサラにして血糖値を下げる
![]() カゼ予防
カゼ予防
![]() がん予防
がん予防
などがあります。
![]() 硫化アリル(アリシン)は空気に触れると効果を発揮する!
硫化アリル(アリシン)は空気に触れると効果を発揮する!
水溶性の硫化アリルを有効に使うためには、生のまま刻みましょう。
空気に触れさせて使うと、より薬効を発揮します。
熱に弱い硫化アリル(アリシン)は加熱すると効能が少なくなります。
水に長くさらすと硫化アリルが流れてしまうので避けましょう。
甘酢漬けにする場合は汁ごと食べると効果的です^^
この2つの成分だけでもかなりの効能が期待されますね。

母が「体に良いから食べなさい」と言っていたのも、よくわかります^^;
ちなみに夏バテ予防の効果的な組み合わせは
・豚肉と一緒に食べる
・細かく刻んだ生のらっきょうを薬味として食べる
ビタミンB¹を含む食材と一緒に食べることで、硫化アリルの効力がアップします。
夏にバテてしまう方は積極的に取り入れてみてはいかがでしょうか。
らっきょうを上手に取り入れて、夏に負けない体を作りましょう!
ここまでご覧いただき、ありがとうございました。
コメント
この記事へのトラックバックはありません。




























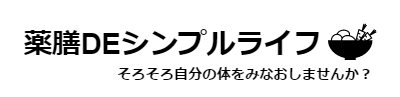
この記事へのコメントはありません。