烏梅(うばい)とは何か?効能と烏梅汁(烏梅湯)の作り方とは?

突然ですが、烏梅(うばい)って聞いたことはありますか?
見た目は真っ黒の大きな干しブドウみたいなんですが、実はこれ、梅なんです。
漢方では昔から健胃整腸や咳止めなどに効果があるとして広く使われているんですが、『梅干し=赤くて酸っぱいもの』という常識を覆してくれるほど、見た目が黒いのです。
実際に烏梅を手に取って見て、???マークが頭いっぱいに浮かんだので、あれこれ調べてみることにしました!
ということで、今回の主役は烏梅さん。烏梅の基本的なことから、効能などについてご紹介します。梅好きさんは要チェックですよ!それでは、レッツうめ~♪
烏梅(うばい)とはなにか?
一般的には馴染みのない品なので、スーパーでも滅多にお目にかかりません。もしかしたら烏梅の存在すら知らない人も多いかもしれません。(私も神戸南京街の林商店さんで初めて本物を見ました。)

見た目が真っ黒のため、初めて見ると「え、これ食べれるの?」と驚いてしまうかもしれませんね。
![]() 烏梅の製造工程で塩は使わない!
烏梅の製造工程で塩は使わない!
烏梅を梅干しと違い、作る工程で塩を使いません。なので梅干しのように塩分が気になる人も、烏梅の場合は気にせず食べることができます。塩分を気にしなくてはいいのは嬉しいですよね。
![]() 実は国産の烏梅は超レア品!生産所はたった1か所だけ!
実は国産の烏梅は超レア品!生産所はたった1か所だけ!
中国から梅や烏梅の製造方法が伝わって以降、日本では昔から奈良県の月ヶ瀬地域で多くの職人が烏梅を作って京都の染色業者に販売していましたが、明治時代以降に化学染料が普及してからというもの、職人の数は年々減少。今では一人の製造者の方が烏梅を作り、文化を伝えているそうです。
※2017年の烏梅作りは終了しましたが、四季折々のイベントがあるので、機会があれば一度訪れてみてください(´ω`*)
では続けて、烏梅の風味や味、用途についてご紹介します!
烏梅の風味と味、用途はなにがあるの?
- 風味は燻製の独特な香り(とてもスモーキーで少し苦味がある)
- 味は芳醇な梅の匂いが入り混じった、強い酸味が特徴
烏梅は生薬として使われる他にも、
- 口紅や頬紅などの化粧品
- ほくろ取りの成分として化粧品に配合されている
- 染料の触媒剤
などなど、幅広く使われているんです。

烏梅はどんな効能があるのか?続けて、中医学的な観点と、西洋医学的な観点から烏梅のことを見てみましょう!
烏梅(うばい)の効能は?
中医学・西洋医学的な2つの観点から、烏梅の効能についてご紹介します。
烏梅の中医学的な効能
![]() 烏梅の効能
烏梅の効能
- 肺の機能を回復させる(斂肺)
- 腸の機能を回復させる(渋腸)
- 唾液分泌を促し、身体に不足している水分を補う(生津)
- 回虫を弱らせ、腹痛を緩和する(安蛔)
烏梅は呼吸器官にまつわる肺や腸、脾臓の機能を回復させ、体を温める性質があるとされています。古くから痰や咳止め、消化不良や下痢などに効果があるほか、のどの渇き、嘔吐しそうな不快な状態(悪心)の改善、回虫の駆除にも用いられます。
![]() 梅は三毒を断つ
梅は三毒を断つ
梅には食べ物の毒、血の巡りの異常、水分代謝の異常を治す効果があることが知られています。
烏梅の西洋医学的な効能
西洋医学の効能のほうが「あ、やっぱり梅は疲労回復に効果あるんだ」と分かりやすいかもしれませんが、中医学と西洋医学の両方の視点で見ても、烏梅の効能はとても高いという事がよく分かります。
烏梅汁とはなんなのか?さっそく簡単な作り方をご紹介します!
烏梅汁(烏梅湯)の作り方!

真っ黒な見た目と独特の風味からは使い方が想像できませんが、そんなときは、まず「烏梅汁」から作ってみましょう!
烏梅汁とは、烏梅を煮出した一番シンプルな飲み物で、烏梅が古くから作られていた中国では「烏梅汁」がとてもポピュラー。煎じ汁には抗菌作用が期待できると言われています(´ω`*)
烏梅汁(烏梅湯)の材料と作り方の工程
![]() 烏梅汁の材料
烏梅汁の材料
- 烏梅5g(2・3粒)
- 水500ml
- 鍋(鉄鍋以外)
![]() 烏梅汁の材料
烏梅汁の材料
- 烏梅と水500mlを鍋に入れ、沸騰するまで強火にかける
- 沸騰後は弱めの中火にし、30分ほど煎じる
- 完成したら、温・冷どちらでもお好みでどうぞ!
ただし、烏梅だけだと酸味や風味が強いので、お好みで砂糖を加えて飲んでください(*^▽^*)

実際に作った烏梅汁を温(砂糖なし)・冷(はちみつ入り)両方で飲んでみると・・・
あ、すごい燻製の風味がする~
酸っぱいけど後味さっぱり~(*’▽’)
口に入れるまでは燻製の香りが強いですが、口に含んでみるとレモン系の酸味で後味はスッキリしてます。強烈な酸味ではないですが、これは好き嫌いが別れそうな味ですね。普段から変わった味のお茶を飲む人には、烏梅汁は苦じゃないと思います。
この他にも上級者向けレシピとしては、台湾式梅サワージュースとも言われる酸梅湯(サンメイタン)もあります。が、これも実際に作ってみようと思いますので、また次回にご紹介させていただきますね(´ω`*)

台湾に旅行に行ったときは酸梅湯をあちこちで見かけました!
ちなみに私が烏梅を購入したのは神戸南京街にある林商店さんなんですが、こちらは通販でも取扱いしてます。そして、これまた近くにあってよくおやつを食べに行く甜蜜蜜(ティムマッマ)さんでも通販の取扱いがあります。
大手通販ではかなり値段が張るので、専門店で安いとこを探してみてくださいね\(^o^)
今回のみたらし的あとがき
梅は保存食、調味料や体調不良時の応急薬としても幅広く使われてますが、まさか青梅を燻製にしたものまであるとは知りませんでした。身近な食材なのに、まだまだ知らないことはたくさんありますね。
そして「生薬」や「薬膳」と聞くととたんに難しく感じますが、今回の烏梅のように、普段は使っている物の変わった一面を知ることができる分野でもあるんです。(薬膳の教科書は漢字多くて難しいですがw)
このブログでは、そういったちょっと難しいものをシンプルにお伝えできればと思いますので、興味が湧いたら引き続きご覧ください(*’▽’)
暑い日が続きますが、今年の夏は烏梅を味方につけて元気に過ごしてくださいね!
ここまでご覧いただき、ありがとうございました♪
和のスーパーフード梅干しのこと
 Copyright secured by Digiprove © 2017-2018
Copyright secured by Digiprove © 2017-2018
コメント
この記事へのトラックバックはありません。
































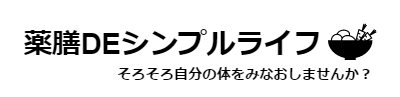
はじめまして♪
今日、ふと『薬膳』が頭に出てきて”そーいえば、薬膳ってなんだろう??”とネットで調べていたら こちらに辿り着きました。
自分の不健康と食生活をなんとかしたい‼と思っております。
いろいろ勉強させていただきます(๑¯ω¯๑)
よろしくおねがいします♪
アイコブーさん、はじめまして(*’▽’)/
管理人のみたらしと申します。
ようこそ&コメントありがとうございます♪
ゆる~い薬膳情報ではありますが、
アイコブーさんの健康と食生活のお役に立てれれば嬉しいです。
またいつでもいらしてください~(´ω`*)